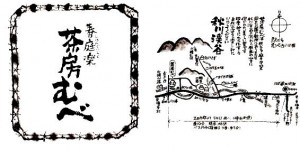朗文堂―好日録014
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
朗文堂-好日録
ここでは肩の力を抜いて、日日の
よしなしごとを綴りたてまつらん
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
米どころだけではない !
アダナ・プレス倶楽部 新潟旅行
會津八一と坂口安吾のこと
Ⅲ

 さて、ここで會津八一(1881-1956)のことをしるさねばならない。坪内逍遙はこのひとを、かくのごとく紹介している。
さて、ここで會津八一(1881-1956)のことをしるさねばならない。坪内逍遙はこのひとを、かくのごとく紹介している。
とにかく君は、天成の藝術家である。
新潟市會津八一記念館のパンフレットやWebsiteでは、かくのごとく紹介している。
會津八一は、秋艸道人シュウソウ-ドウジン または渾齋コンサイと号し
すぐれた東洋美術史学者でもあり
それとともに、類まれな歌人であり
また、独往の書家でもあった
《會津八一記念館と北方文化博物館新潟分館・會津八一終焉の地》
會津八一記念館 は日本海の潮騒が聞こえそうなほど、関谷浜に沿った高台にあった。おりしも企画展《會津八一 vs 北大路魯山人 ── 傲岸不遜の芸術家》の開催中であった。
會津八一(1881-1956)と、北大路魯山人(1883-1959)は、ほぼ同世代人であり、互いに書にたくみでありながら、書芸家だけとしての人生を過ごさなかったという共通項を有する。
すなわち會津八一は、新潟市古町通五番町・料亭會津屋に三男五女の次男としてうまれた。1881年8月1日うまれだったから八一と名づけられたとされる。歌人であり、美術史家であり、教育者でもあった。
いっぽう北大路魯山人は、京都にうまれて、名は房次郎。書と篆刻で名を成し、のちに料理と食器の研究と製作にあたった。そんなふたりだったが、両者の仲はそうとう険悪だったそうである。同館ではそんな展示をていねいに展開していた。
しかしながらやつがれ、学芸員諸氏の苦労は別として、こういった個人を顕彰するのが主目的の記念館で、根っこから切りはなされたような、そして被収蔵者の生前の息づかいや、体温のぬくもりのごときものが感じられない、博物館的な施設は苦手である。つまりこういう個人の記念館施設なら、わざわざ新潟まででかけなくても、バスでチョイの 早稲田大学會津八一記念博物館 で十分な気がする。それよりも、やつがれ、會津八一が意味なく苦手であることにあらためて気づかされた。
會津八一は生前、みずからを《傲岸不遜 ゴウガン-フソン》と称していたそうである。「傲岸 ゴウガン」は、おごりたかぶり、角立って、へりくだらないこと。「不遜 フソン」は、謙遜でなく、おもいあがっていることである。
すなわち《傲岸無礼》の類語であって、《傲岸不遜》などとみずから称するなどというものではない。むしろ天にむかってうそぶくものである。もちろんそこには諧謔やパラドクスがあったにせよ、なにか避けたいものがある。
早早に記念館を抜けだして外で一服していたところ、山崎歯科博士がさりげなく、
「この近くに、ふんいきのよい、會津八一関連の施設がありますけど、いきますか?」
とかたりかけてきた。このあたりの山崎博士の呼吸はまことにそつがない。
會津八一は早大卒。名を成してのち、東京下落合霞坂に居住し、のち1935年(昭和10)目白文化村に引っ越した。そこは霞坂時代の「秋艸堂」と区別するために「文化村秋艸堂」と呼ばれるようになった。ところが1945年(昭和20)4月13日の夜半、目白文化村は B29 の大編隊による空襲を受け、會津八一が長年にわたって蒐集した美術品や骨董品、あまたの美術資料や書物が一夜のうちにすべて灰になった。
このころ會津八一は「養女」きい子とともにあり、空襲のなかを逃げまどい、同年4月中に、「養女」きい子をともなって郷里の新潟に疎開、蒲原郡中条町の丹後康平宅にしばらく寄寓した。その疎開とは混乱をきわめた列車の旅ではなく、毎日新聞社の取材用の飛行機によった。會津八一はやはり傲岸不遜のひとであった。
そして新潟市南浜に瀟洒な邸宅を提供されてからは、ここを「南浜秋艸堂」と名づけて、二度と東京にもどることはなく、この地で1956年(昭和31年)11月21日、75歳で永眠した。
會津八一記念館から車で移動するほどでもないところに、「南浜秋艸堂、會津八一終焉之地」はあった。ところがナント、そこは昨夜から一日だけ宿泊し、博物館巡りをしてきた「北方文化博物館の新潟分館」であった。ふたたび北方文化博物館のWebsiteから紹介する。
《ゆったりとした時間が流れていた南浜秋艸堂》
會津八一は母屋の和風建築に居住したというより、おもにこの建物の正面からみて右手、2階建ての洋館に居住したようである。ふたつの建物はすっかり整理されて、會津八一と良寛の書があふれていた。
ここでやつがれ、おもわずのけぞった。最初はウソだろうとおもった。展示場でも陽の射しこむ母屋の展示場の端に、まったく無造作に良寛の書『天上大風』があった。これは夢かうつつか? わからん!
かつてやつがれ、某氏と某社とともに、「小町・良寛」という、写植用仮名書体の開発に関わったことがある。この仮名書体は、現在ではデジタル・タイプとして発売されている。その際、良寛の書をそれなりに勉強した。とりわけ『天上大風』の書は、何度も(書物で)みたし、その飄逸な書がきわめつきにすきだった。その原本がここにあった!
ガラスケースの中の書だったから、写真はひどいがご容赦願いたい。
ともかく、この書軸を無造作に掛けてあることに驚いた。
もしかすると良寛和尚は『天上大風』を何枚も書いていたのかもしれない。
あるいはこれはレプリカか?
それでは伊藤文吉8世に失礼になる。
『天上大風』を前にして、やつがれうろたえるばかり。
同館では図録や資料集は製作されておらず、若い受付嬢がいるばかりで詳細は不明のまま。
今回の旅では良寛記念館に行けなかったことは既述した。すなわち、どうしても良寛記念館にもいかなければならないことになったようである。すなわち越後路の旅、ふたたび。
南浜秋艸堂の庭の片隅に1955年(昭和30)に建立された歌碑がある。碑文は以下のようである。
かすみたつ はまのまさこを ふみさくみ
かゆき かくゆき おもいそわかする
 この碑の建立にあたって會津八一は上の写真のような指示を、原稿に朱筆で書き加えている。「歌碑として 彫刻せしむるために 特に 筆劃に 訂正を 加へたる ものなり 彫工は熟練なるを要す 文字行間のあきは 絶對に原稿の 通りにすること」
この碑の建立にあたって會津八一は上の写真のような指示を、原稿に朱筆で書き加えている。「歌碑として 彫刻せしむるために 特に 筆劃に 訂正を 加へたる ものなり 彫工は熟練なるを要す 文字行間のあきは 絶對に原稿の 通りにすること」

さてと……、短歌と書に関しては論及する立場にない。しかし會津八一は、書字と刻字、書写系の文字と彫刻系の文字の相違に関しては理解不足を指摘されてもしかたなかろう。
ここにみる建立直後の写真は、おそらく刻字の部分に石灰でも入っていたとおもわれる。したがって文字は鮮明に読みとれる。それで八一翁は満足したらしい。
しかしやつがれ、この碑の彫刻のあまりの彫り込みの浅さと、線質の弱さ、かぼそさにおどろいた。筆画や字配りにこだわって指示をだすのはかまわない。そしておそらく、彫工はしかるべき技倆の名工を起用したと想像されるが、その指示のきびしさに萎縮し、細部にこだわりすぎて、本来の技倆をまったく発揮していないとみた。とくに運筆の速度の遅速感が、彫刻からはまったく伝わらなかった。
こうしたひら仮名異体字をふくむ、いわゆる和様の書の彫刻は、1898年(明治31)長崎の父祖の地に建立された『平野富二君碑』(平野幾み《喜美子》書、現在は谷中霊園乙11号14側、平野家墓地に移転)が、彫りの深浅、柔軟な線質を石彫にいかしてみごとである。その報告は平野富二没後110年を期して『富二奔る』(片塩二朗、朗文堂、2002年12月3日)にまとめた。
また長崎公園の『池原香穉翁小伝』の碑も、艶冶な和様の書を刻した巨大なものであり、名碑といってよいであろう。長崎の寺町通りの寺(名前は失念)には、會津八一のできばえのよい、かなの書の碑もあったと記憶している。會津八一翁はこれらの名碑をご存じなかったか。
會津八一の書は「孤高蒼古の境地にある」とされる。残念ながらその良さがこの歌碑にはいかされていなかった。ましてそこに「原字と石彫指示書」があっただけに、余計痛痛しかった。やつがれは、八一翁にならって現在の碑面に触れ、文字をそっとなぞってみたが、採拓の形跡はほとんどないのに、あまりに弱弱しい刻字であった。
写真は照明もなく、やつがれの技倆の悪さがもろにでているが、それでも 6 枚シャッターを切ってこの程度のものしかなかった。「餅は餅屋」という。あまりひとの職能に容喙するのは良い趣味とはいえないこともある。
《會津八一とふたりの養女――きい子 と 蘭のこと》
會津八一が妻帯したという記録は、ほとんど関心もなかったので管窺に入らない。しかし會津八一記念館の記録に、晩年の會津八一をめぐるふたりの女性が「養女」として登場する。そして「會津八一終焉の地・北方文化博物館新潟分館」には、「養女」きい子と、「養女」蘭の数葉の写真記録がのこされていた。
會津八一63歳 1944年(昭和19)
身辺の世話をする高橋きい子(義妹)を養女にする。
會津八一64歳 1945年(昭和20)
養女きい子疎開先で病没する。享年33(7月10日)。
會津八一68歳 1949年(昭和24)
従兄弟・中山後郞の娘・蘭を養女とする(5月)。
きい子は、ともに東京目白で空襲の猛火のなかを逃げまどったひとである。そのあまりにも若い永眠のときとは、敗戦となるひと月ほど前のことであった。この1945年7月10日には會津八一はまだ南浜秋艸堂には移転しておらず、蒲原郡中条町の丹後康平宅でのことであったとおもわれる。
それでも目白時代のものか、戦前のきい子と八一がともに庭に出て、庭いじりをしている写真がのこされている。きい子は整った顔立ちで、真っ白な割烹着を着て、まるで若妻のようにはなやいでみえる。
きい子の逝去から2週間後ほどして、1945年7月25日から會津八一は南浜秋艸堂に移転した。そして4年後に蘭を「養女」としている。蘭も越後の美人といってよい、引き締まった顔立ちである。どことなくきい子と似ていなくもない。
奏楽家の宮城道雄(1894-1956)が新潟を訪れた際、蘭はその琴の指導をうけた。それを見まもる會津八一の顔は、ムスメを見る顔というより、むしろ(あきらかに)、いとしいひとをみるという顔をして写真に収まっている。
會津八一の評伝や研究書は数多いが、このふたりの「養女」に触れたものはすくないようだ。やつがれ、これらの写真から、孤高を演じ、傲岸不遜をうそぶいていた會津八一が、澄みきった心境にいたったときにチラリと見せた、人間らしい一面をみるおもいがして、勝手に救われた。
《坂口安吾 風の館》
坂口安吾(1906-55)は新潟市中央区西大畑町にうまれた。第2次世界大戦後に、在来の形式道徳に反抗して「堕落論」をとなえたひとである。1946年(昭和21)4月『新潮』に掲載された「堕落論」は青空文庫にアップされているので見て欲しい。
かつての新潟市長公舎が「安吾 風の館」として、坂口安吾の諸資料を収集して無料公開されている。 磯馴れ松がひろい庭を占めていた。これがよかった。

その「安吾 風の館」からすぐ近く、新潟大神宮参道の脇に「安吾生誕碑」がある。碑面には以下のようにある。 安吾らしくアッサリしていた。たしかにこのあたりは、日本海の荒波が押しよせてきそうな海浜の地であった。
私のふるさとの家は 空と 海と 松林であった
そして吹く風であり 風の音であった
 《そして、短かった新潟の旅は終了した。でも、すぐにもう一度行きそうだな?》
《そして、短かった新潟の旅は終了した。でも、すぐにもう一度行きそうだな?》
かくして短かった新潟の旅終了。雨男が同行したにもかかわらず、終始アッパレ日本晴れだった。そしてやつがれ、諸橋轍次記念館で漢学酔い、笹川流れで船酔い、北方博物館とその関連施設で魑魅魍魎のごときもろもろの出現でぬかるみに。かにかくに……、あらためておもうに、心地よいばかりの興奮の旅であった。新潟でサポートしてくださったおふたりに感謝。
最後は「豪農の館」でボケをかましているショットで終わろうか。
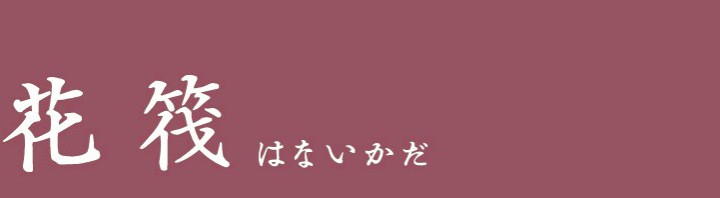

































 新潟は、信濃川(やつがれの郷里・信州信濃では、おもに千曲川という)と、阿賀野川がなした沖積層と、海と砂丘と湊町からつくられた街である。
新潟は、信濃川(やつがれの郷里・信州信濃では、おもに千曲川という)と、阿賀野川がなした沖積層と、海と砂丘と湊町からつくられた街である。