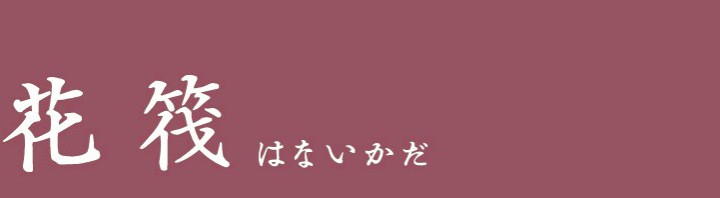活字書体判断における三原則
1. 判 別 性 Legibility レジビリティ
活字書体におけるほかの文字との差異判別や、認識の程度。
2. 可 読 性 Readability リーダビリティ
文章として組まれたときの語や、
文章としての活字書体の読みやすさの程度。
3.誘 目 性 Inducibility インデューシビリティ
視線を補足して活字書体などの情報に誘うこと。
またはその誘導の程度。
★ ★ ★
これらの外来語由来のタイポグラフィ専門用語は、耳慣れないことばかもしれない。また、本来は活字版印刷術 ≒ タイポグラフィの業界用語であったから、簡易版の英英辞典や英和辞典には掲載されていないものがあるし、紹介があっても混乱しがちである。
したがって、その翻訳語としての紹介(日本語)は混乱の極地にある。なにも外来語をありがたがるわけではないが、近代活字版印刷術 ≒ タイポグラフィが、江戸最末期から明治初期に海外諸国から招来されたため、その基本用語のおおくが外来語になっている。それは現代のパソコン業界用語とされる、 PostScript, PDF, DDCP など、もはや翻訳語すら追いつかなくなった現状に鑑みたら仕方ないことだろう。
そのためもあって、わが国における活字書体の差異判別や特徴をかたることばは混乱しがちであり、あいまいな感覚語をもちいたり、共通基盤を有さない印象論が大手をふるってかたられている。しかしこれらのことばは活字書体の評価や判断にあたってたいせつなことばである。タイポグラファなら、あるいはタイポグラファたらんとする有志の皆さんは、ぜひとも記憶していただき、適切に使用していただきたい。
《 詳 細 解 説 》
《判別性 Legibility レジビリティ》
判別性は、大文字の「B」が、数字の「8」に見えたりするときや、大文字の「I」 アイ、小文字の「l」 エル、アラビア数字の「1」イチがはっきりと区別できなかったり、大文字「O」オーと、数字の「0」ゼロが明確に区別・判別・識別できないときなどにもちいられる。わが国では、漢字の「網」と「綱」、「ー」オンビキ、チョウ- オン-フ と「-」ダッシュの差異判別や、カタ仮名の「ロ」 ロ と、漢字の「口」 クチが見分けられるように、活字を製作したり、それを議論するときなどにもちいられる。Legibility の和訳語はなかなか定着せず、従来は可視性・識別性・視認性などともされてきた。
Legibility は形容詞 legible から派生した名詞で、文字が読みやすいこと、文字の読みやすさ、文字の判別や識別の程度――判別性・識別性などをあらわす。活字版印刷術が創始されてから間もなく、すなわち1679年にその初出がみられる。形容詞の legible は、筆跡や印刷された文字が、看取される、判別可能な-という意味である。そのほかにも、容易に読める、読みやすいという意味で、後者の比較語(confer)としては readable がある。
こうした判別性を、19世紀末から20世紀初頭に活躍した、英国のタイポグラファのエリック・ギルは、
「A は A、B は B である」
というフレーズをしばしば挑発的に口にしたとされる。また著書『エッセイ・オン・タイポグラフィ』にも各所にしるしている。この「A は A、B は B である」とは、たとえば A という文字を成立させている、画線の組合せでしかない図形を、どう書けばもっとも A らしくなるのかということである。逆にいえば、A を構成しているどの線をどう歪め、どうくずせば A ではなくなるのかという、字体(文字の骨格)の限界の追求を、アルファベットのすべてについて試みることであろう。
文字が成立した長い歴史におもいをはせれば、文字誕生の神秘とその洗練の過程には、確たる文字の姿(字体)を獲得するにいたった人間の工夫と、そのために「定まった字型 Type」をもつ活字のはたした役割の重要性に気づくはずである。文字はひとしく万人のものであり、それゆえに公的な存在であり、その最大多数が迷うことなく、ひとしく判別できる字体(文字の姿・骨格)を探し出す努力は、タイポグラフィの実践者や、活字書体設計にたずさわる者にとっては、基本的な問いかけといえよう。
《可読性 Readability リーダビリティ》
可読性とは、漢語調で、いかにもふるくからあったという語感で納得させられるが、意外にあたらしい活字版印刷界の業界用語である。もとはドイツ語で Lesbarkeit の英訳語の名詞で、読みやすいこと、読めること、可読性という意味と、面白く読める、面白く書いてあることをあらわすのが原義である。
英語での Readability の初出はあたらしく、 1843年にはじめての使用をみる。わが国ではおそらく明治期に、たれかが Readability に「可読性」という、じつにうまい訳語をあたえたものと想像される。『広辞苑』には 「かどく-せい 【可読性】 読み取れる性質・度合い」 とされている。また一部にこれを「速読性」としたいというむきもある。
1980年代後半、アナログからDTPへの過渡期――技術の継承期――には世界規模での混乱がみられた。そのころ膨大に出版されたアメリカの資料の一部には、レジビリティはフォントを表わし、リーダビリティはファンクションを表す――などという記述も見られた。なにをいっているのか分からなくなる記述が出現し、困ったことに、いまでもそうした資料を引くむきがみられる。
要するにこのことばは、文字の見分けやすさと、文字の読みやすさのこと。つまりタイポグラフィの基本的役割に関わる用語である。したがってタイポグラフィ関連やデザイン関連の洋書に触れると頻出するので、あらためて確認していただきたい。すなわち、あまりこれらのことば自身を難しく考えないで、むしろタイポグラフィの基本的な役割が「文字の見分けやすさと、その読みやすさ」であることを確認したいものである。
《誘目性 Inducibility インデューシビリティ》
英語の形容詞 「Inducible = 誘致[誘引]できる;誘導できる;帰納できる」の名詞形である。名詞形の Inducibility としての初出はきわめてふるく、印刷術の創始から間もない1643年のこととされる。すなわち「視線を補足して、活字書体などの情報に誘うこと。またはその誘導の程度」をあらわすために、活字版印刷の業界用語として登場したので、簡易版の英英辞書、英和辞書などには未紹介のものが多いようである。
誘目性が重視されるのは、サインデザインや広告の世界が多い。空港や駅頭で、的確な情報を提供し、そこに視線を誘導することは、文字設計者の重要な役割でもある。またポスターやカタログなどの商業広告においても、旺盛な産業資本の要請にこたえて誘目性を重視した書体も開発されてきた。
産業革命以後、この誘目性が活字書体設計に際して「ディスプレー書体」などとして強く意識されるようになり、黒々とした、大きなサイズの活字が誘目性に優れているという誤解も生じた。しかしながら、もともと「Display」は動物の生得的な行動のひとつで、威嚇や求愛などのために、自分を大きく見せたり、目立たせる動作や姿勢のことで、誇示・誇示行動をあらわす。
もちろん、現代では「Display」は、表示・展示・陳列などの意でも用いられるし、コンピューターの表示・出力として、図形・文字などを画面に一時的に表示する装置にも用いられる。ところが原義とは怖ろしいもので、ディスプレー書体の多くは、誘目性を過剰に意識するあまり、あまりに太かったり、奇妙・奇抜なデザインに走って(判別性と可読性に劣ったために)、一過性の流行の中に消滅してしまったものも少なくはない。活字の世界で求められるのは、まず第一義的には、判別性と可読性であり、誘目性はむしろ抑制したほうが無難なようである。
ところが近年、バリア・フリーの考え方が進化して「ユニバーサル・デザイン」が提唱されるにおよんで、電子活字書体の一部が「UDフォント」などと称しはじめた。ここでの文字情報の役割は、判別性とともに、誘目性が重視されるようになった。まだわが国の「UDフォント」は開発の第一段階にあるようだが、ここにあげた《活字書体判断における三原則》に立ち帰り、地に足のついた、真の「UDフォント」の開発をめざして、進化・発展して欲しいものである。